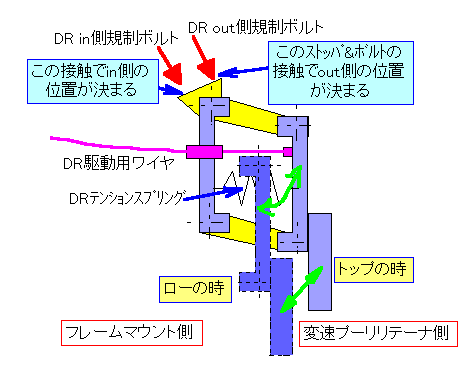|
最新更新日:2000.2.27 ・メンテナンス メンテナンスはできるだけやってるつもりです。山の中でトラブルが起こると最悪の場合、MTBを放棄して人間だけ帰るということもありえます(後日取りに行くのもめんどうです)。とはいっても構成部品点数も少ないMTBの事ですので基本メンテもさほど大変では有りません。自分の命を乗せているものと考えて自分の手でやってみてはいかがでしょう。(ちなみにkitoは自分以外の手による整備は正直に申し上げて信頼してません。)
できれば機構も理解していると緊急時にも役に立つのではないかと考えます。 |
|
|
Contents 文字列をクリックして下さい。ジャンプするようにしてあります。
|
|
|
洗車 メンテの基本は洗車だと思っています。これはモトクロス時代からそう思い続けています。洗車をすると何が良いかというと、マシンにじっくり近づいて見るので、故障などを発見できるのです。フレームのクラック、変形、リムの接合部の開きなどなど。
走行中におかしいことに気がつけば良いのですが、そうでないと次へ持ちこしてしまう危険性があります。また、洗った後は水切りを兼ねて軽く走ってみるのですが、この時も異常に気がつくときです。
まず、洗い方ですが、相手は金物ですので界面活性剤(洗剤)などは使わないようにしたいものです。雑誌なんかでは業者さんに頼まれて洗剤を使うような事を書いてますが大変疑問です。車を洗うときに洗剤を使っている人がいますがあれもどうか?と思ってます。汚れはワックス(コンパウンドの入ってないもの)等で落とすのが基本です。
また塗装部などはガソリンや洗い油等は変色の原因になります。水でチョロチョロとかけて、手などで汚れを落とすようにして洗います。水の圧力が高いと軸受け内に入って、ベアリングは錆びると良い事なしです。 また、リムはブレーキの粉が付着していますので、使い古し(別に新品でもいいですが)の歯ブラシなんかでコシコシこすって洗います。自転車の場合、洗う時間はそれほどかかりません。20分?くらいでしょうか? 洗った後はフロントをアップさせた状態にして、チェーンステイのエンド端の内側の穴から水を抜きます。このような穴がないときはシートピラーを抜いて逆さまにでもするんでしょうか?。水はよく抜きましょう。
ワックスはカーボン素材や樹脂素材などは相性が有ると思いますから確認するのがベターでしょうね(どこへ?)。鉄やアルミの塗装は大抵の場合、問題ありません。ただ、コンパウンドの入ったものは塗装面を削ってしまうので黒用のものなどのワックスオンリーの物がおすすめです。
|
|
|
各部の注意点と交換時期
|
|
|
ネジなどを締めるときの注意点 これはたいていの機械要素のネジ部に言えることだと思いますが、ネジ部にはグリスを塗り、ボルトの座面は無潤滑で行くのがいいです。というのはネジ部には後述の理由と強烈な圧力がかかり焼き付きや錆が発生し易いため。また座面は緩み止めになるのとそれほど圧力がかからないため。
ボルト締結はボルトが締めつけられて伸びることにより部材を圧着させて、その時に部材間に発生する摩擦力により締結します。ネジ部に錆などが発生しているボルトを締め込んだ場合、締込みのトルクが錆などの摩擦力に取られてしまい、十分にボルトを引き伸ばすことが出来ずに締結不良を起こします。またボルトのネジ部に潤滑材を塗ると締付けトルクがボルトを引き伸ばす力により使われるので締結力は増します。ただ、自動車のホイールの取り付けボルトなどの様にメーカーが「ネジ部に潤滑材を塗ってくれるな」、と言ってるものはその限りではありません。
ただ、自転車で注意するべき問題は異種材料の締結がよく行われることです。異種金属をくっつけると多かれ少なかれ電位が生じて電気が流れます。この電気により材料がいたんでしまうことがあるのです。この場合、焼き付きやかみ込みを起こし易いので座面にもグリスを塗った方が良いと思ってます。 自転車のネジ部の潤滑材としてはリチウム系のグリスが良いと思ってます。グリスは大別してリチウム系とカルシウム系、モリブデン系、シリコン系に分けられます。
ホームセンターなどで万能グリスとかで売ってるものはたぶんリチウム系だと思います。リチウム系は値段は高いですが極圧性能や耐水性に優れています。ベアリング等に使います。
カルシウム系はシャシグリスといってトラックなどの下回りに使われます。値段が安いです。 モリブデン系は上述のものと違い、2硫化モリブデンの微粒子で構成されてまして、この微粒子が部材の間でつぶれることなく存在出来るので、極圧性能に極めて優れます。ただ、値段は高いです。
シリコン系は油に侵される樹脂などの潤滑に使われます。樹脂部分になにかグリスを塗るとなるとこのタイプでないと樹脂を侵してしまいますので注意して下さい。 またネジ部に塗る量ですが、目的が焼き付き(カミコミ)防止などですのでうすく、均一に塗ります。厚く塗ると締め込んだ時はグリスの固さもあり一時的に締まったように見えますが、時間がたつにつれてグリスが流れて隙間が出来てゆるみの原因になります。
また、ベアリングにグリスを入れる場合は多めに入れます。というのはグリスがベアリングの放熱を助けるからです。たとえば10tトラックのハブの中には2Lくらいのベアリンググリスが塗り込んであります。ちなみに摩擦抵抗を極限まで減らして耐久性を犠牲にしてもスピードを・・・・という場合はグリスよりも柔らかいオイルがいいでしょう。
また最後にネジ部などの組み付け時の注意ですが、必ず手を使い締まらなくなる所まで締め込みましょう。はじめから工具を使うとネジを斜めにねじ込んでしまったりしかねません。
|
|
|
グリスとオイルの違いと注意点 注意点から。自転車には鉄をはじめとする金属以外のものが多く使われています。普通のグリスやオイルのケミカル剤は金属相手のものなので樹脂にかけると材料を侵してしまうことがありますので十分に注意して下さい。たとえばフロントフォークのオイルシール部にCRC556等をかけるとかをするとシールを傷めてしまう事とがあります。 ケミカル剤のラベルを見て判断できれば良いのですが材質名そのものが書いてある場合が多くて何が何やらという感じです。僕が教わったことはケミカル剤のノズルが樹脂でできているものは侵しにくいが金属のノズルがついているものは用途を考えなくてはいけないというものです。はたしてこれが正しいかは??ですが実際的な知識として紹介しておきます。
次にグリスとオイルの違いです。グリスとオイルの主な目的は潤滑ですが構造と使用法がちょっと違います。
オイルはいわゆるオイルです(^^;。用途は潤滑、冷却、シール、洗浄、圧力伝達等でしょう。特徴は流動性があり、潤滑能力に優れ、浸透性もあり、機械を傷めないという感じですね。一般的にはギアオイルやエンジンオイル、または油圧機械の作動油などです。
自転車ではチェーンオイルとかサスペンションの中のオイルです。オイルと一言に言っても用途に合わせて固さ、対樹脂侵食性、揮発性、極圧性能、浸透性といろいろな項目がありますので細かく言うとややこしいです。僕はオイルはチェーンにさすくらいしか使っていません。その他の部品はすべてグリスを塗って仕上げています。
最近は自転車にもディスクブレーキも出てきましたのでブレーキオイルもあります。ブレーキオイルは特殊なオイルでゴムは侵さないのですが塗装面や樹脂は強烈に侵しますので十分に注意しましょう。このため自動車の世界ではブレーキオイルと言わずブレーキフルッドと呼んだりします。
グリスは石鹸の中にオイルを練り込んだものです。石鹸の分子の網目の中にオイルが染み込んでいわばスポンジの中にオイルが染み込んでいると言うとイメージし易いでしょうか?
このため流動性は低く、浸透性は低いですが、極圧性能にすぐれています。ただ、熱を受けると石鹸の分子が切れたり、オイルの流動性が上がり、グリスは流れてしまいます。また、くりかえし強烈なストレスを受けると同じく分子が破壊され極圧性能が落ちます。ということでグリスも定期的に交換してあげる必要があるわけです。
また流動性が低いことからダンパーに使われることもあります。自転車の世界ではあまり見ませんがスクーターの安いものにダンパーとして使っているものがあります。
|
|
|
BBの交換 上述のようにクランクと同調したパキパキ音がかなり耳につくようになったので交換しました。交換には2つのアタッチメントが要ります。ひとつはクランクを外すもの。これは1500円くらい。ついで、BBを回すためのもの。「シマノのBBを外すアタッチメント」といえば買えると思います(700円くらい)。また、このアタッチメントを回すために32mmのスパナも要ります。
外すときのコツはアタッチメントをクランクを締め込むボルトで外れないようにするとナメなくて良好です。適当にワッシャーを組み合わせてスペーサを作るとより良いでしょう。
BBの締付けトルクはなかなか激しいのでナメやすく、何回もナメると外れなくなる恐れがあります。あれが外れなくなったらもうフレーム交換かパキパキ音をずっとガマンするかになってしまいます。 下の画像は上が3年間使ったBB(UN-51/107/68)で、下が新しく(1998.5.3)入れたBB(UN-72/107/68)です。新しいものは約100g軽くて、700円高い、というのを天秤にかけて決めました。
また、下の画像はBBを抜いたハンガー内部です。旧BBからの錆がアルミに付着しているのが分かります。まあ外観なので錆びていようがどうでもいい様に考えますが、錆はその他の材質の酸化等を促進することがありますし、錆びたことにより膨張してネジが外れなくなるということもあります。
組み上げる時の注意点はBB抜いた後、ハンガーの中はいろいろと汚れていますので、きれいに拭き上げます。僕はエアー(4kg/cm2)で吹いた後、ウェスで拭きます。それから、各ネジ部、そして、BB本体とアダプターの接触部にグリスを塗って組み上げます。
また、クランクをセットする時もクランク軸にグリスを塗って組み上げます。
|
|
|
ホイールのフレ取り ホイール、特にリアホイールは良くふれます。景気よく下るとたいていフレます。フレるとどうなるかというと、ブレーキにあたり、シュッシュッとする音がします。程度が軽いときは気にするかどうかの問題ですが、重傷になると走行抵抗になります。
フレをとるにはニップル回しを使います。詳しくは本屋で立ち読みするかしてください。難しくありません(横フレの話ですが)。注意点はスポークには普通の右ネジが切ってあります。ということはニップルはメスなわけで、要するによく考えてやれば問題はないということです(^^;。 kitoはパークツールの#14、15用(SW-2)を使っています。ニップル回しはイイモノを使わないとニップルをなめてしまいなんともならなくなる可能性がありますのでアゴのしっかりしたものを使ってます。これは使いやすくていいです。
ただ、僕のようにVブレーキとカンチレバー用ブレーキを組み合わせて使う場合はリムとブレーキシューのクリアランスがシビアですのでこまめにフレはとらないといけません。まあ、洗車の後にはリアホイールのフレ取りがあると思っておけば気も楽です。
フレ取りのサイズはニップルのサイズで決まります。買う時はスポークのサイズを言って買うと間違いが無いでしょう。
|
|
|
変速機の調整 新車のときはしっかり変速できたギアも走り込むとダンダンおかしくなってきます。そんな時は要調整です。前も後ろも同じようなものです(前の方がチョイ面倒)。
変速機はシフターとディレイラー(以降DR)をワイヤーでつないで動かしています。動作不良時はこの3要素を全部解決する必要があります。反対に言うとこの3つだけなのです。
ワイヤーは切れているか、伸びてしまったか。伸びてしまったら、後述のDRの調整を読んでください。切れていたら新しいワイヤーにはり直して、DRを調整します。 シフターのメンテは指定個所にグリスを塗る、泥詰まりを無くすくらいメンテらしいメンテはしません。壊れたら交換でしょうね。
さて、DRの調整ですが、準備するものはメーカーが出しているメンテの仕方のマニュアルです。基本的にこれに従います。僕の場合はサイスポ別冊の"Cycle Tuning Book
1996"の中のシマノの手順書を見ています。不思議な事ですが、この手順にしっかり従った時は変速もパチパチ変って気持ち良いです。ちなみにこのムック(雑誌の特集号みたいなもの)は良いと思ってます(洗車のところ等はいただけませんが)。
まあ、この手の本はたいてい同じ事がかいてあるので大同小異です。ただ、気をつけないといけない所はああいった写真がたくさん載っているものは裏焼きしてしまって気がつかずに出版してしまった所もあります。メンテの本で裏焼きして有るとかなり頭はこんがらがります。できれば裏焼きできないたとえばシマノの説明書みたいなものが良いと思ってます。
DRの基本構造は簡単なものです。inとoutの動作規制ボルト2本、ワイヤーテンショナーでおしまいです。シフトの量はシフター側で決定しています。 たとえば、リアで話をすると、8速(トップ側)のギアのところでout側の動作規制ボルトをキメます。ついで、1速(ロー側)のギアのところでin側の動作規制ボルトをキメます。次にワイヤーを指定されたテンションまで張ればOKです。分かり易いかどうか分かりませんが、DRの構造のマンガを書きました。参考にしてください。
また、フロント側はまず、in側の動作規制ボルトを決めて、out側も同じ感覚ですがちょっとトライ&エラーを繰り返す必要があると考えています。気分的にはちょっと外まで動くようにする感じです。
|
|
|
ブレーキの調整 調整項目は遊びの調整とVアームの位置の調整です。両方ともそれほどややこしくありません。kitoの場合、適当な間隔でO/Hしています。
遊びはブレーキレバーのワイヤーが刺さっているアジャスターで調整します。それで調整幅を吸収できなければ、ブレーキ側のワイヤーを止めているボルトで大まかに調整して、再度レバー側のアジャスターを調整します。
Vブレーキを着けていると、フロントタイヤの脱着の時にレバー側のアジャスターでワイヤ長さを長くして、引っかけ部分を外しますから、上の調整はタイヤを外すことを前提に行います(後輪の場合も)。
Vブレーキは一日くらい走ると左右のアームの動く量が変わってくることが良くあります。この時はスプリングの調整ネジで左右のアームのバネ力を調整します。
ここはよく変わるのでこまめにチェックしたいところです。ブレーキレバーから入力して、左右のVアームが同じように動くかどうかを見るわけです。
kitoはブレーキはできるだけ早く動いて欲しいのでスプリングは最も強く効く状態にしてあります。もっと反力が強くても良いと思ってます。
|
|
|
フロントサスのメンテナンス kitoはSHOWAのグラビエを使っていまして正直ほとんどノーメンテナンスです。他の製品を使っている人にはなんの参考にもならないかもしれませんね。グラビエの場合やることはただ一つ、エア圧の調整のみです。またへたにCRCの様なものを吹き付けるとオイルシールが壊れてしまいますので要注意です。 エア圧調整はそれほどややこしくありません。専用のポンプがあると作業が楽です。左右のエア圧を同じにすることです。kitoはRSタイチの注射器型を使っています。 僕のグラビエDHはエア&金属スプリングの併用なのでエア圧が低く(0.5kgf/cm2G)、チェックをしてもそれほど変化をしていないのですが、3kg/cm2ほど入れるサスの場合はしばしばチェックしないと結構変化している場合があります。
|
|
|
パンク パンクは定期的なメンテナンスでないかもしれませんが、ここへ書きます。MTBはそれなりの頻度でパンクします。山の中でパンクして直せないとなんともならないのでぜひ自分で直せるようにしておきたいものです。 MTBのパンク修理はそれほどややこしくありません。オフロードバイクに比べたらトコロテンを食べるより簡単です。ホイールを外して、タイヤのビードを落として、タイヤレバーでチョイチョイです。やり方は本や雑誌等にすでに出ています。
パンクの原因のほとんどがリム打ちです。リム打ちとはチューブがタイヤとリムに挟まって穴があく現象のことです。主な原因は空気圧の不足です。走る前は必ず空気圧をチェックしましょう。エア圧はタイヤサイドに書いてある値の真ん中くらいが良いです。高くするとよく跳ねるようになります。
気をつける所はちょっと書き出します。 1.組み上げる時にチューブをリムとビードの間に挟んだまま空気を入れない事。そのまま空気を入れていくとチューブが裂ける事があります。空気を入れる前に面倒でもチューブが挟まってない事を確認しましょう。 2.組み上げ後、バルブのナットをつける前に空気を軽く入れてみてバルブが垂直にセットできたかをチェックしましょう。この時点で垂直になってないとバルブとバルブ穴の位置がずれています。これはバルブにストレスを与えるので面倒でもバルブの位置をしっかり出します。空気をかなり抜いてビードがリムの上を滑らせて修正します。(ホイールを回転させて地面に接触させてタイヤとリムを滑らせます。文字でかくとなにがなんだか分かりませんが、実際の作業はとても簡単な作業です。)
3.バルブのナットはkitoははめません。これはモトクロス時代の名残ともいえます。モトクロスではホイールとリムは比較的簡単にズレてしまうため、バルブにナットをかけておくとバルブの所にストレスがかかって、バルブの所からチューブが裂けてしまうと言われていたため。ナットをつけておかないとバルブが傾ぐのでストレス状態が分かります。ちなみにモトクロッサーにはこの現象を起こし難くするためにビードストッパーというものでリムにビードを機械的に強く押し付けています。
4.ワンタッチ式の半透明のシール状のやつはイマイチ信頼が置けないというのが正直なところ。表面の処理(削って突起が無いようにする作業)をしっかりやれば問題無いそうですが、kitoは実績のあるのり&パッチを使ってます。ただ、この時注意すべきことはノリは大事なときにはチューブの中から蒸発していて使えないことが多いと言う事です。このためスプレー式のものを使ってます。これならばシールがしっかりしているため蒸発してるということがありません。
|
|
|
メールアドレスはトップページの下です。 |
|